Introduction
フジッコのDX推進グループで活躍するN.Tさんは、営業や商品企画の経験を活かし、業務の効率化と営業力の強化に貢献しています。今回は、彼のこれまでの歩みや、DX推進プロジェクトで感じている手応え、そして未来への展望について伺いました。
プロフィールProfile
DX推進グループ所属。2013年にフジッコに入社し、愛知県や北陸エリアで6年間の営業経験を積む。その後、商品企画や業務用営業を経て、2022年にDX推進グループへ異動。現在は、業務プロセス改善とデジタルツールの導入に力を注いでいる。
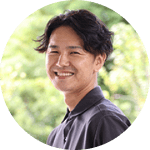
01DX推進グループへの転身と
そのきっかけ
DX推進に挑戦しようと思った理由は?
コロナ禍がきっかけで、デジタル化の重要性を強く感じました。それまで直接お客様とコミュニケーションを取るのが当たり前でしたが、対面での機会が激減し、データやデジタルツールを使って情報を集める必要性が増しました。そんな中で、フジッコでもDXの推進が必要だと考えるようになり、社内公募制度を通じてDX推進グループに異動することを決意しました。
DX推進グループでの仕事内容を教えてください
DX推進グループでは、業務効率化や業務改善、営業力の強化を目指してさまざまなデジタルツールの導入や業務改革に取り組んでいます。例えば、チャットボットや生成AIを使った自動化ツールを導入し、社内の問い合わせ対応の削減を試みたり、クラウドシステムの活用による情報共有の効率化を行いました。デジタルツールを積極的に活用することで、従業員のデジタルアレルギーをなくし、働きやすい環境を作ることも目標にしています。

02DXの魅力とやりがい
DX推進に携わっていて嬉しかったことは?
DX推進の仕事は、自分が考えたことをカタチにできるのが魅力です。従業員が働きやすくなる仕組みを作り、それが実際に成果として現れたときは非常にやりがいを感じます。また、会社全体がデータ活用や業務効率化に向けて意識を変えつつあることも感じており、フジッコがデジタル化を積極的に進めていることを実感しています。
意外な難しさはありましたか?
DX化に取り組む中で感じた意外な難しさは、社内の理解を得ることです。新しいツールや考え方を導入する際に、全員がすぐに受け入れてくれるわけではありません。しかし、少しずつコミュニケーションを重ね、対話を通じて意識改革を進めることが重要だと感じました。
03今後の目標とDXの未来
今後の目標は何ですか?
DXには終わりがないと思っています。常に変革を続け、現状に疑問を持ち、改善していくことがDXの本質です。今後はフジッコ全体でデータを活用し、すべての部署が効率的にコミュニケーションを取りながら、お客様により良い商品やサービスを提供できる環境を作っていきたいです。データドリブンな文化を社内に根付かせ、全社員がデータを活用できるような組織を目指しています。
求職者へのメッセージ
フジッコでは、熱意や行動力を持っている人が活躍できる環境があります。社内公募制度などを通じて、自分のやりたいことに挑戦できるチャンスが多くあります。私も、DX推進グループで新しい取り組みに挑戦し続けています。デジタル化や業務効率化に興味がある方、会社の未来を変えるような仕事に挑戦したい方には、ぜひフジッコで一緒に働いてもらいたいです。


N.Tさんのキャリアパス
Schedule
とある1日のスケジュールをご紹介いたします。
-
9:00~
PC起動(出勤)、チャット・メールの確認
-
10:00~
IT業者と打ち合わせ(オンライン)
-
11:00~
他部門とプロジェクトMTG
-
12:00~
昼休憩
-
13:00~
デジタルツールのメンテ・調整
-
14:00~
他部門とプロジェクトMTG
-
15:00~
作業時間(資料・企画書・セミナー受講)
-
16:00~
IT業者から
サービス・ツール紹介・業界動向把握 -
17:00~
プロジェクトの進捗をタスク管理で更新しておく。プロジェクトスケジュール管理も行う。
-
17:30~
夕礼(その日のトピックや共有事項をG内で報告)
-
18:00~
明日のスケジュールを確認し、帰宅




